【重要なお知らせ】弊社へのご登録情報のご確認および更新に関するお願い
という件名のメールが届いていないでしょうか?
結論から言うと、このメールはフィッシングサイトへ誘導する詐欺メールなので開かないようにしましょう。
実際のメール内容
実際に届いたメールも載せておきます。
From:︶えきねっと
Subject:【重要なお知らせ】弊社へのご登録情報のご確認および更新に関するお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会員様へ、
━━━━━━━━━━━━━2023-05-13━━
いつも「えきねっと」をご愛顧いただき、ありがとうございます。
インターネット上の不正行為の防止、サイトとしての信頼性・正当性を高めるため。現在弊社では、お客さまがご登録いただいている各種情報について、最新の情報かどうかを確認をさせていただいております。
大変お手数ではございますが、下記URLからログインいただき。
⇒https://www.eki-net.com
========================
■ご依頼の背景
========================
近年、複雑化・高度化する金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止への対応がますます重要となってきております。弊社におきましては、金融庁および経済産業省が公表している「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえ、お客さまが弊社にご登録いただいている各種情報等について、現在の情報に更新されているかどうかを確認させていただいております。お客さまにはお手数をおかけすることとな
========================
なお、アカウントが退会処理された場合も、新たにアカウント登録(無料登録)していた だくことですぐに「えきねっと」をご利用いただくことができますので、今後もご愛顧いた だけますようよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本文中に記載のURLは開かないでください
本文中のURLをクリックすると以下のようなページが開きます。
※メール記載のURLは表記上は https://www.eki-net.com となっていますが、実際のURLは https://www.eki-net.com.hoasrgm.fit/ となります。
こちらのページは実は公式のえきねっとのログインページとほぼ一緒。
公式サイトだと誤認させて入力を促す手口ですね。
ご注意ください。
入力してしまうとどうなるか?
実は・・ 恥ずかしながら私はこの「えきねっと」のフィッシングメールに一度引っ掛かったことがあります・・。
当時はメールの内容も少し違って、2年間利用がないので更新しないと失効します・・的なものだった気がします。
えきねっとの利用頻度って私は数年に1回くらいなので、確かに最近ログインしてなかったなぁとあまり疑いなく入力してしまいました。ご丁寧にクレジットカードまで・・
普段ならこの手のに引っ掛かることはないんですが、確かあまり思考が働いてない状態で無意識にやってしまったんですよね・・ 気を付けないとですね。
ちなみに、その日の夜にオンラインショッピングでクレジットカードを使おうとした際になぜか使えなかったことで気が付きました。カード会社が勝手に止めてくれていたようです。
お陰様で特に被害はありませんでしたが、もちろんカードはそのまま利用停止で再発行処理となりました。1週間程度で再発行されたのでその間使えなかったくらいで事無きを得ましたが、何気にカード番号とセキュリティコードが良い番号で気に入っていたのでそこだけ残念でした・・・
あとは入力してしまったID・パスワードは色んなサービスで流用しているものだったので思い当たるものは全て変更対応しました。結構数があったのでこれは時間的に厳しかった・・
というわけで、当然ですが良いことないので皆さん気をつけましょう。
ツイッターでの反応
対処方法は?
こちらのメールを受信した場合はメールを破棄しましょう。
メールを開いてしまっても、記載のURLを開かないようにしましょう。
もしURLをクリックしてしまったら?
万一URLをクリックしてしまった場合は、即ブラウザを閉じましょう。
絶対にフォームに入力はしないよう注意してください。
まとめ
『【重要なお知らせ】弊社へのご登録情報のご確認および更新に関するお願い』というメールはフィッシング詐欺メールです。
受信しても開かずに破棄することを推奨いたします。
詐欺メールには注意しましょう。


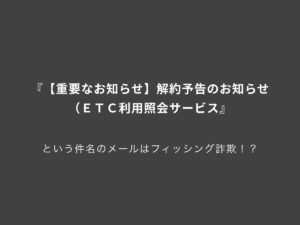
コメント